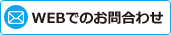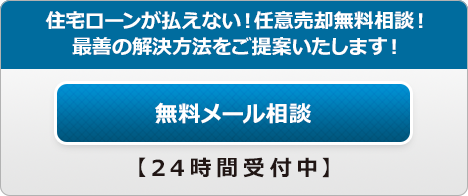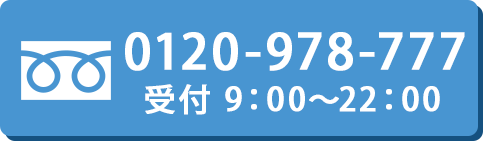不動産購入時の税金
不動産の購入時の税金をご紹介します。

執筆者:家原哲生
株式会社テスコーポレーション 営業主任
宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士

不動産購入時の税金
不動産取得税
不動産取得税とは
不動産を取得した時に取得した者に課せられる都道府県税で、課税標準は固定資産税評価額を使用します。
但し、土地については、特例により令和6年3月31日までに宅地評価土地を取得した場合の課税標準が固定資産税評価額の1/2に軽減されます。
(1)税率
| 標準税率 | 土地・住宅 3% | 非住宅の建物 4% |
|---|
※本則税率は4%ですが、土地及び居住用の建物の取得については、令和6年3月31日まで特例により、税率が3%になります。
(2)特例
①住宅に係る課税標準の特例(地方税法73条の14)
下表に該当する住宅を取得した時は、住宅の課税標準から一定額を控除することができます。
| 適用対象 | 要件 | 軽減内容 |
|---|---|---|
| 新築住宅を取得した場合 | (ア)住宅の用に供する(貸家住宅も可) (イ)床面積が50㎡(戸建以外の貸家共同住宅は40㎡)以上240㎡以下 | 住宅の課税標準から1戸につき1200万円まで控除 |
| 既存住宅を取得した場合 | (ア)取得した者が自己の居住の用に供する (イ)床面積が50㎡以上240㎡以下 (ウ)昭和57年1月1日以後に新築された既存住宅または、地震に対する一定の安全基準に適合している既存住宅(注1) (エ)人の居住の用に供されたことがない既存住宅も可 | 新築年月日の区分に応じ住宅の課税標準から下記の金額を控除する(注2) |
(注1)以下の既存住宅も対象になります。
①地震に対する安全基準に適合しない既存住宅を取得し、6ヶ月以内に耐震基準に適合するための改修を実施した後に入居した場合
②宅地建物取引業者が取得した既存住宅(新築後10年以上)について、一定の増改築等を行った上、取得の日から2年以内に耐震基準適合要件、または一定の省エネ性能を満たすものとして個人に販売し、その個人の居住の用に供された場合(平成27年4月1日~令和5年3月31日までの取得)
(注2)新築年月日の区分に応じた住宅の課税標準から控除額
| 新築年月日 | 控除額 |
|---|---|
| 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
| 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
| 昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
| 平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1000万円 |
| 平成9年4月1日~ | 1200万円 |
②住宅用土地に係る軽減措置の特例(地方税法73条の24)
前記①の特例に該当する住宅の敷地となる土地を、下記の条件のもとに取得した場合は、次の(a)、( b)のいずれか多い金額が土地の取得に係る税額から控除されます。
| 新築住宅の敷地(住宅と同時に取得) | 未使用の住宅を新築後1年以内に取得 |
|---|---|
| 新築住宅の敷地(住宅より先に購入) | 敷地取得後2年以内(注)に住宅を新築 |
| 新築住宅の敷地(住宅より後に購入) | 敷地取得前1年以内に住宅を新築 |
| 中古住宅の敷地(住宅より先に購入) | 敷地取得後1年以内に住宅を取得 |
| 中古住宅の敷地(住宅より後に購入) | 敷地取得前1年以内に住宅を取得 |
(注)令和4年3月31日までは3年(やむを得ない事情がある場合は4年)以内
(a)150万円×3%=45,000円
(b)土地1㎡あたりの価格×1/2(特例による軽減)×住宅の床面積の2倍(※)×3%
※住宅の床面積は、1戸あたり200㎡が限度となります。
登録免許税
登録免許税とは
不動産を取得して所有権移転登記や保存登記または抵当権設定登記などをする時に課せられる国税です。
(1)税率
| 登記などの種類 | 課税標準 | 本則税率 | 特別税率 |
|---|---|---|---|
| (a)所有権保存登記 | 不動産の価格 | 0.4% | - |
| (b)所有権移転登記 (ア)売買等によるもの(注) (イ)相続・法人の合併 (ウ)贈与・遺贈 (エ)共有物分割(現物分割は除く) | 不動産の価格 | (ア)2.0% (イ)0.4% (ウ)2.0% (エ)2.0% | 1.5% |
| (c)地上権・永小作権・賃借権または採石権の設定・転貸 | 不動産の価格 | 1.0% | パーツの追加・変更・削除・移動 |
| (d)抵当権の設定、先取特権の保存、質権の設定 | 質権の全額、極度金額または不動産工事費用の予算金額 | 0.4% | - |
| (e)地役権の設定登記 | 承役地の不動産の個数 | 1件に付1,500円 | - |
| (f)抵当権、先取特権、質権の移転登記(相続または法人の合併による移転登記) | 債権金額または極度金額 | 0.1% | - |
| (f)抵当権、先取特権、質権の移転登記(その他の原因による移転登記) | 債権金額または極度金額 | 0.2% | - |
| (g)抵当権の順位の変更登記 | 抵当権の件数 | 1件に付1,000円 | - |
| (h)仮登記 (ア)所有権保存・移転 (イ)その他のもの | (ア)不動産の価格 (イ)不動産の個数 | (ア)1.0% (イ)本登記の税率の1/2 | - |
| (i)附記登記・登記の更正 | 不動産の個数 | 1件に付1,000円 | - |
(注)土地売買のみ(令和5年3月31日まで)
(2)住宅用家屋の軽減税率(租税特別措置法72条の2、73条、75条)
次の要件に該当する個人の住宅用家屋(その個人の住宅の用に供する家屋。土地を除く)に係る登記については下表の軽減税率が適用されます。
①新築住宅
・令和4年3月31日までに新築または取得した個人の住宅用家屋であること
・床面積が50㎡以上であること
・新築または取得後1年以内に登記すること
②既存住宅
・令和4年3月31日までに取得した個人の住宅用家屋であること
・床面積が50㎡以上であること
・取得日時点で建築年数が耐火建築物25年以内(それ以外は20年以内)。それを超える場合は、地震に対する一定の安全基準に適合していること(既存住宅売買瑕疵担保保険に加入している一定のものを含む)
・取得後1年以内に登記すること
| 登記事項 | 課税標準 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 所有権保存登記 | 家屋の価格 | 0.15% |
| 所有権移転登記 | 家屋の価格 | 0.3% |
| 抵当権設定登記 | 債権金額 | 0.1% |
※令和4年3月31日までに取得した新築の認定長期優良住宅または認定低炭素住宅(どちらも個人の住宅用家屋)は、所有権保存登記及び所有権移転登記の税率が0.1%(一戸建の認定長期優良住宅の所有権移転登記は0.2%)に軽減されます。
(3)特定の増改築がされた住宅用家屋の所有権移転登記の軽減税率(租税特別措置法74条の3)
個人が令和4年3月31日までに宅地建物取引業者が特定の増改築等をした一定の既存の住宅用家屋を取得し、1年以内に登記した場合は、当該住宅用家屋の所有権移転登記の税率が0.1%に軽減されます。
(4)相続に係る所有権移転登記の免税(租税特別措置法84条の2の3)
①土地を相続した者が諸油研の移転登記を受けないまま死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から令和4年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とする所有権移転登記をする場合は免税となります。
②個人が平成30年11月15日から令和4年3月31日までの間に、市街化区域外の土地で法務大臣が指定する土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合で、その土地の価格が10万円以下であるときは所有権移転登記を免除します。
印紙税
印紙税とは
売買契約書、請負契約書等の課税文章に納付義務がございます。
(1)印紙税の特例(租税特別措置法91条)
平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書及び建築工事の請負に関する契約書に係る印紙税は下表のように軽減されます。
| 不動産売買契約書に記載された金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 10万円超50万円以下 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 6万円 |
| 5億円超10億円以下 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下 | 32万円 |
| 50億円以上 | 48万円 |
(2)文書の種類と印紙税の取扱い
| 文書の種類(例) | 印紙税の取扱い |
|---|---|
| (a)不動産の売却、購入、賃貸、貸借、斡旋などの申込書 (b)仲介手数料契約書 (c)不動産の媒介契約書(※業者同士の媒介契約書では課税されることもあり) (d)重要事項説明書 (e)媒介業務報告書 | 課税文書に該当しません |
| (f)不動産購入申込書 | ・販売会社保存用で、別途売買契約書を作成する旨が記載されている場合は、課税文書に該当しません ・申込者保存用は不動産の譲渡に関する契約書に該当 |
| (g)不動産売買契約書 (h)土地賃貸借契約書 (i)不動産交換契約書 | 記載金額に応じて算定 |
| (j)車庫賃貸借契約書 | 課税文書に該当しません |
| (k)借地権譲渡契約書 | 記載金額に応じて算出 |
| (l)登記承諾書 | 課税文書に該当しません |
相続税
相続税とは
被相続人の遺産を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ場合に、その遺産総額となる金額が一定の金額を超えるとかかる税金で、金額に応じた相続税率が適用されます。
(1)基礎控除額
基礎控除額=定額控除額3,000万円+法定相続人比例控除額(1人あたり600万円)×法定相続人の数
(2)相続税の速算表
| 法定相続分に応ずる各取得金額 | 税率 | 速算控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超 10,000万円以下 | 30% | 700万円 |
| 10,000万円超 20,000万円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 20,000万円超 30,000万円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 30,000万円超 60,000万円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 60,000万円超 | 55% | 7,200万円 |
【計算例】
課税遺産総額(相続財産の課税価格の合計額から基礎控除額を差引いた残額)が1億2千万円、相続人が配偶者、長男、次男の3人の場合。
①法定相続分 配偶者1/2、長男1/4、次男1/4
②各相続人の取得金額
配偶者 1億2千万円×1/2=6,000万円
長男 1億2千万円×1/4=3,000万円
次男 1億2千万円×1/4=3,000万円
③各相続人の相続税額
配偶者 6,000万円×30%-700万円=1,100万円
長男 3,000万円×15%-50万円=400万円
次男 3,000万円×15%-50万円=400万円
④相続税の総額
1,100万円+400万円+400万円=1,900万円
(配偶者の税額控除は考慮していません)
(3)配偶者の税額軽減(相続税法19条の2)
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が次の(a)(b)のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからない制度です。
(a)1億6千万円
(b)配偶者の法定相続税相当額
(4)相続時精算課税制度(相続税法21条の9)
①概要
財産の生前贈与を受けた場合、贈与時に贈与税をいったん支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計して計算した相続税から、既に支払った贈与税を控除することができます。
贈与と相続を通じて納税するもので、贈与者ごとに通常の贈与税(暦年課税制度)と本制度のどちらか選択して適用することができます。
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限がありません。
②適用要件
(a)60歳以上の贈与者から20歳(令和4年4月1日以後は18歳)以上の子(推定相続人)または孫が受贈したものであること。
(b)本制度を選択する最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署長に対してその旨の届出書を贈与税の申告書に添付すること。
③税額の計算
(a)本制度の選択をした場合は他の財産と区別して贈与税を支払いますが、本制度に係る贈与税は、贈与財産の価格の合計から、複数年にわたり利用できる2,500万円(非課税枠)を控除した金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
但し、本制度を利用すると、暦年課税制度の基礎控除(110万円)の適用はありません。
(b)本制度を利用した場合の相続税は、本制度に係る贈与財産(贈与時の価格)と相続財産を合算して通常の方法で計算した相続税から、既に支払った贈与税相当分を控除します。
その際、相続税額か控除しきれない場合は還付されます。
(5)住宅取得に係る相続時精算課税制度の特例(租税特別措置法70条の3)
令和3年12月31日までに、自己の居住の用に供する一定の家屋を取得または増改築等するための資金(その敷地とともに取得する場合の土地等の取得資金及び住宅の新築等(贈与を受けた年の翌年3月15日までに行われたものに限る)に先行して取得する土地等の取得資金を含む)の贈与を受けた場合は、贈与者の年齢に関係なく相続時精算課税制度を適用することができます。
①適用要件
(a)贈与者から20歳以上の子(推定相続人)または孫が受贈した住宅取得資金であること。
(b)取得または新築する住宅、その敷地の取得資金の贈与を受ける場合、その翌年3月15日までに居住の用に供したとき、または居住の用に供すると見込まれるとき。
(c)取得または新築する住宅の面積が50㎡以上あること
(d)既存住宅においては、取得日時点で築後年数が耐火建築物25年以内(それ以外は20年以内)。それを超える場合は地震に対する一定の安全基準に適合していること(既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものを含む)
(e)増改築等の場合は、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替等で、当該増改築等の工事費用が100万円以上であること、増改築後の床面積が50㎡以上であること、その他の要件を満たすこと。
②税額の計算
通常の相続時精算課税制度と同様です。
贈与税
贈与税とは
その年の1月1日から12月31日までの1年間に親族の他、第三者を含む個人から贈与を受けた財産価格を合計し、その合計額から基礎控除110万円を控除した残額に応じて下表の税率を乗じ、贈与税額を計算します。
贈与税の速算表(特別税率:20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の税率、一般税率:特別税率以外の税率)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 (特例税率) | 速算控除額 (特例税率) | 税率 (一般税率) | 速算控除額 (一般税率) |
|---|---|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 | 10% | 0円 |
| 200万円超 300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
| 300万円超 400万円以下 | 15% | 10万円 | 20% | 25万円 |
| 400万円超 600万円以下 | 20% | 30万円 | 30% | 65万円 |
| 600万円超 1,000万円以下 | 30% | 90万円 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 1,500万円以下 | 40% | 190万円 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超 3,000万円以下 | 45% | 265万円 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 4,500万円以下 | 50% | 415万円 | 55% | 400万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 | 55% | 400万円 |
(1)配偶者控除(相続税法21条の6)
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に最高2,000万円までの控除できる特例です。
適用要件
①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われること。
②配偶者から贈与された財産が、自分の住むための居住用不動産であること、または居住用不動産を取得するための資金であること。
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、または贈与を受けた資金で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けたものが実際に住んでおり、その後も引き続き住む見込みがあること。
(注)配偶者控除は同じ配偶者の間では、一生に一度しか適用を受けることができません。
(2)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(租税特別措置法70条の2)
20歳以上で、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下のものが、令和3年12月31日までにその直系尊属から受ける住宅取得等のための金銭の贈与については、一定の非課税限度額(取得の時期、家屋の種類により300~3,000万円)までは贈与税が課されません。
但し、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅(床面積が50㎡以上240㎡以下)を取得し、居住の用に供するか、遅滞なく居住の用に供することが確実であると見込まれる必要があります。
↓お急ぎの方はまず電話で無料相談↓