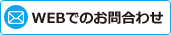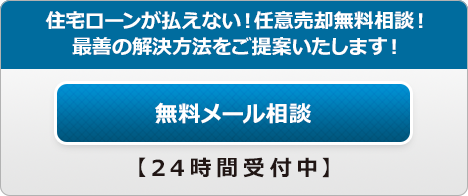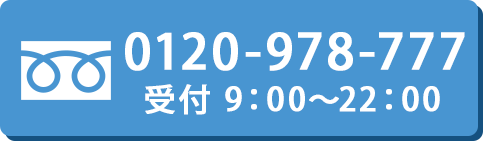不動産保有時の税金
不動産の保有時の税金についてご紹介します

執筆者:家原哲生
株式会社テスコーポレーション 営業主任
宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士

1.固定資産税/都市計画税
(1)税率
固定資産税
税率は1.4%(標準税率)としています。
地方税法によって各市町村は条例でこれと異なる税率を定めることができるため、全国一律とは限りません。
都市計画税
制限税率は0.3%で、市町村で課すことができる上限の税率です。
(2)固定資産税の特例
| 区分 | 軽減の内容 | |
| 土地 | 小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡以下の部分) | 課税標準となるべき価格の1/6を課税標準とする |
| 土地 | 一般用住宅用地(200㎡を超える部分、住宅の床面積の10倍までの住宅用地) | 課税標準となるべき価格の1/3を課税標準とする |
| 建物 | 新築住宅 a.一定の要件を満たす中高層耐火建築住宅 b.一定の要件を満たすa以外の住宅 | 5年度間、税額が1/2になる(120㎡相当分まで) 3年度間、税額が1/2になる(120㎡相当分まで) |
(3)都市計画税の特例
| 区分 | 軽減の内容 | |
| 土地 | 小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡以下の部分) | 課税標準となるべき価格の1/3を課税標準とする |
| 土地 | 一般住宅用地(200㎡を超える部分、住宅の床面積の10倍までの住宅用地) | 課税標準となるべき価格の2/3を課税標準とする |
(4)宅地に係る固定資産税の税負担の調整措置
固定資産税評価額をそのまま課税すると、評価替えに伴い急激な税負担が考えられるため、「負担水準」に応じた負担調整措置がとられます。
以下の負担調整措置は、平成30年度から令和2年度の固定資産税に適用されます。
①住宅用地
次の計算式によって求めた「負担水準」に応じて、なだらかな税負担となるように、前年度の課税標準額に次の表の負担調整率を乗じた額を課税標準額とします。
負担水準=前年度の課税標準額/当該年度の評価額×住宅用地特例率(注)×100
(注)住宅用地の課税標準の特例により、1/6または1/3
| 負担水準 | 課税標準額 |
| 100%以上 | 当該年度の評価額 |
| 100%未満 | (a)前年度の課税標準額 (b)当該年度の評価額×住宅特例率(1/6または1/3)×5% (a)+(b)=課税標準額 ※この計算式で求めた(a)+(b)が(b)の計算式で求めた額の20%を下回る場合は20%相当額とし、 100%を上回る場合は負担調整を行いません。 |
②商業地等(住宅用地以外の宅地)
次の計算式で求めた「負担水準」に応じて、なだらかな税負担増となるように、前年度の課税標準額に次の表の負担調整率を乗じた額を課税標準額とします。
負担水準=前年度の課税標準額/当該年度の評価額×100
| 負担水準 | 課税標準額 |
| 70%超 | 当該年度の評価額×70% |
| 60%以上 70%以下 | 前年度の課税標準額(据え置き) |
| 60%未満 | (a)前年度の課税標準額 (b)当該年度の評価額×5% (a)+(b)=課税標準額 ※この計算式で求めた課税標準額(a)+(b)が(b)の計算式で求めた額の60%を上回る場合は 60%相当額、20%を下回る場合は20%相当額となります。 |
(5)令和元年度または令和2年度における土地価格の特例
固定資産税評価額は基準年度から3年間据え置くことを原則としていますが、令和元年度または令和2年度においてさらに地価の下落傾向がみられる場合は、土地についての価格を簡易な方法で修正することができます。
(6)商業地等に係る税負担の減額措置
商業地等の固定資産税は、負担調整措置により負担水準70%とした場合を上限としていますが、地方公共団体の条例により負担水準60%~70%の範囲内により算定される税額まで減額できる措置を講じることができます。
(7)宅地に係る都市計画税の税負担の調整措置
宅地に係る都市計画税については、固定資産税と同様の負担調整措置がありますが、市町村の判断で据え置き等の措置を講じることもできます。
(8)タワーマンション専有床面積の補正
区分所有に係る建物の専有部分は、1棟の建物全体に係る税額を専有部分の床面積の割合によって按分するのが原則ですが、平成30年度から新たに課税される居住用超高層建築物(注)については、階層別専有床面積補正率により補正します。
(注)居住用超高層建築物:高さ60mを超える建築物のうち、複数の階に住戸が所在しているもの(いわゆるタワーマンション)をいいます。
↓お急ぎの方はまず電話で無料相談↓